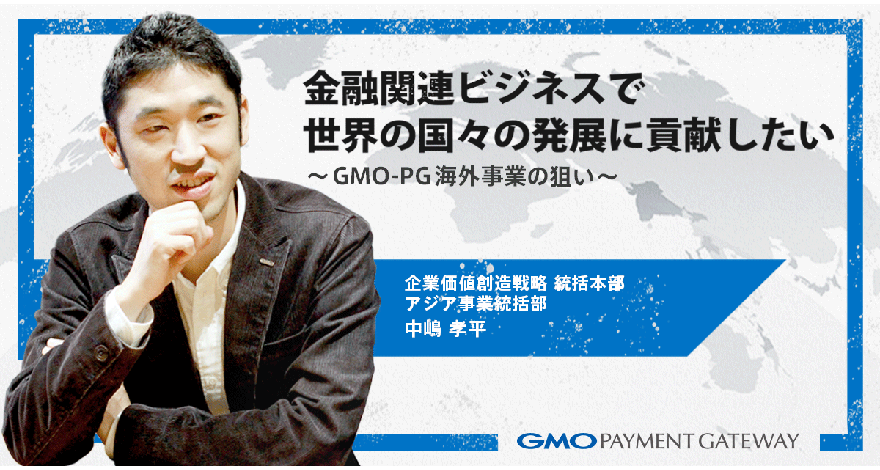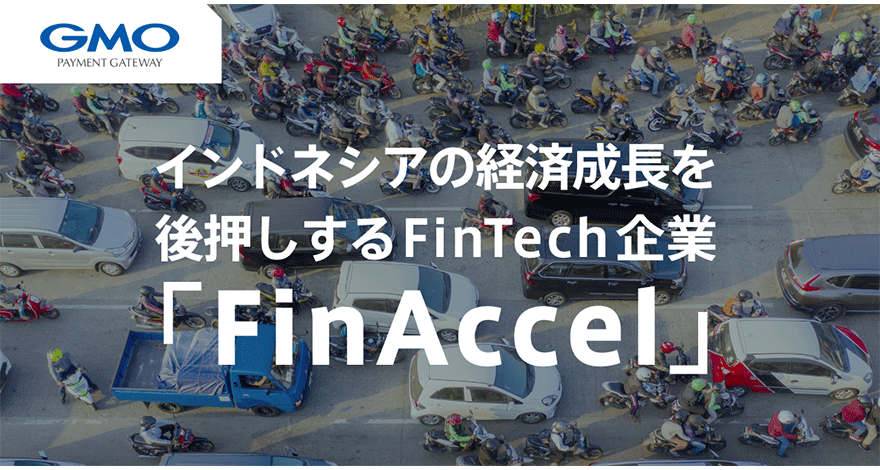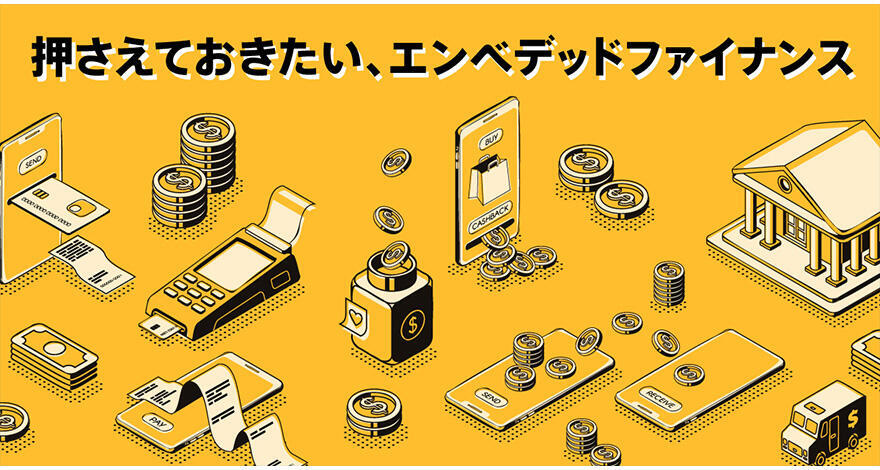FinTech(フィンテック)は、金融とIT(情報技術)を組み合わせた革新的なサービスや事業領域などのことで、私たちの生活に身近なものも数多く存在します。すでに当たり前のように使っているサービスがFinTechだったということもあるでしょう。
金融とITを融合させる取り組みはこれまでもあり、今後もさらに新しい技術を組み合わせて便利なサービスが生まれると考えられます。主に欧米におけるFinTechの変遷や日本国内における具体的なサービス事例などを紹介していきます。
FinTech(フィンテック)とは

FinTechとは、Finance(金融)とTechnology(技術)を合わせた造語で、金融サービスとITを組み合わせたサービスや事業領域などのことを指します。FinTechの取り組みは以前からありましたが、インターネットやスマートフォンの普及により、さらに数々の便利なサービスが生まれ、私たちの生活に身近なものとなっています。
FinTechの変遷
FinTechの歴史は意外と古く、1866年頃から始まっています。Arner, Barberis, Rossの論文※1によると、FinTechはいくつかの変換期を経て現在は、FinTech3.0 の時代と呼ばれています。FinTechの歴史を簡単に振り返ってみましょう。
・FinTech1.0
1866〜1967年までがFinTech1.0と呼ばれる時期です。1866年、アメリカで最初の大西洋横断ケーブルが引かれ、1918年にはフェドワイヤーによる電信やモールス符号を使った電子送金システムが完成しました。
・FinTech 2.0
FinTech 2.0は、1967〜2008年までの期間を指します。1967年に初のATMをバークレイズが設置し、1970年代には、世界初のデジタル証券取引所 NASDAQと、海外へ多額の支払いができる相互金融機関の通信プロトコルSWIFT(スイフト:国際銀行間通信協会)が設立されました。また、1980年代からはオンラインバンキングが普及し、人々の金融機関の認識を大きく変えた時代でもあります。
1998年にはPayPalが登場し、オンライン化とともに新しい決済システムの登場を予感させます。しかし2008年の世界金融危機により、この時代のFinTechは終わり、次の時代のイノベーションに繋がります。
・FinTech 3.0
2008年~現在に至るまではFinTech 3.0のフェーズに入っています。金融危機が起こったことで、銀行に対する信頼が欠如すると同時に、規制が変更されたことで新たなプロバイダーが市場を開拓していきます。ビットコインが2009年に誕生すると、ブロックチェーンを使った多数の暗号資産が次々と生まれました。またスマートフォンが普及し、現在はスマートフォンから金融サービスにアクセスすることが一般的になっています。
FinTech 2.0時代の従来の銀行からの脱却がFinTech 3.0を定義する要素といえるでしょう。新しい技術が解放され、第三者が金融データにアクセスできるオープンバンキングを使うことで、デジタルバンキングサービスを以前よりも容易につくることができるようになったのです。いわゆるBaaS(Bank as a Service)プラットフォームが銀行など金融機関のレガシーシステムからの脱却を促し、ネオバンクの立ち上げを実現しました。
※1 Ross Buckley, Douglas W. Arner, Janos Nathan Barberis, January 2016, "The Evolution of Fintech: A New Post-Crisis Paradigm?", SSRN Electronic Journal: 47(4):1271-1319, (2022年10月13日取得, https://www.researchgate.net/publication/313365410_The_Evolution_of_Fintech_A_New_Post-Crisis_Paradigm)
FinTechのサービス例
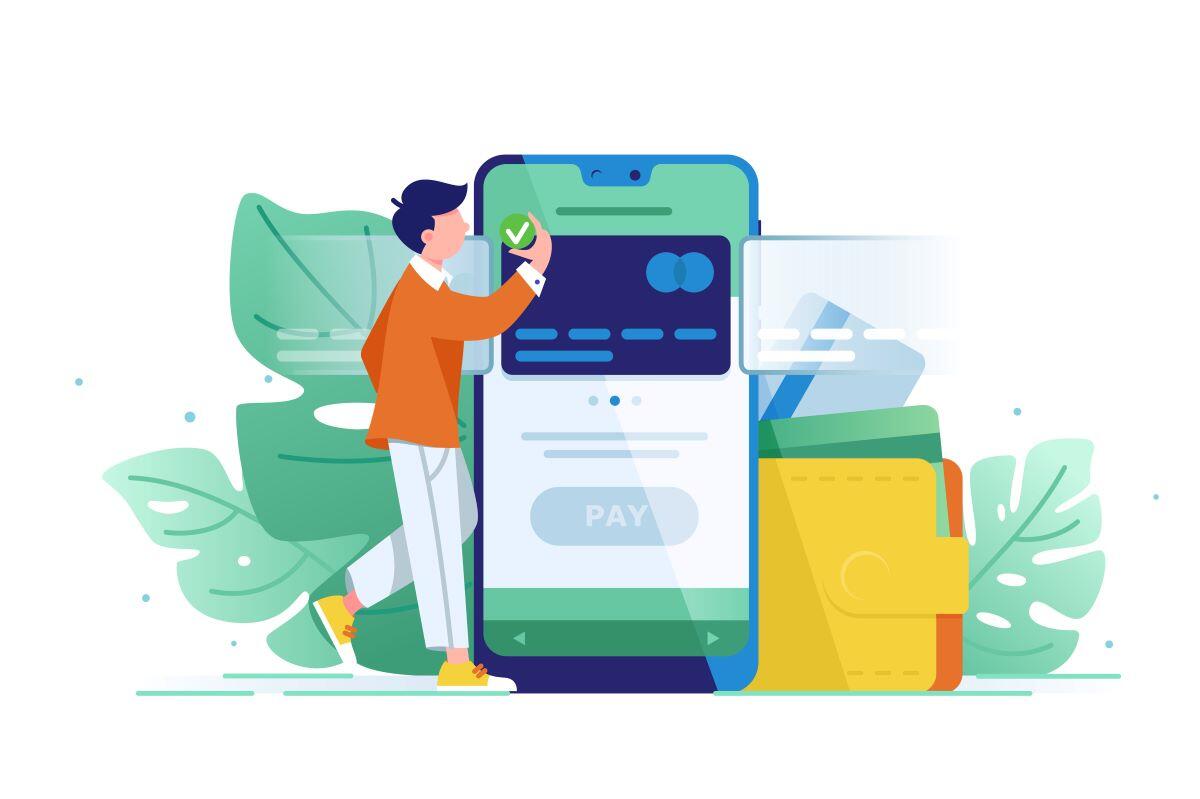
ここからは、日本でも身近になってきたFinTechのサービスを紹介します。
キャッシュレス決済
キャッシュレス決済とは、文字通り現金を使わない決済方法です。クレジットカードをはじめ、QRコードを読み取って支払うスマホ決済、ユーザー同士で送金が可能なPayサービス、あらかじめ金額をチャージして使うプリペイドなど、様々な決済方法があります。
暗号資産(仮想通貨)
暗号資産は、インターネット上の電子データでやり取りされる財産的価値です。
専門取引所を通せば、暗号資産をドルやユーロ、円などに交換できます。またインターネット上の決済で利用することも可能です。ブロックチェーンの技術により、仮想通貨のデータのコピーや改ざんができなくなったことで、より安全性の高い取引が実現しました。
クラウドファンディング
「群衆(クラウド)」と「資金調達(ファンディング)」を組み合わせた造語で、オンラインで不特定多数の人から資金を調達することです。寄付や購入、投資や融資など様々な方法があります。
起案者が事業内容や趣旨、目的などを公開して、それに賛同した人が資金を提供します。誰でも提案でき、少額から気軽に出資できる点が人気です。
関連記事:CAMPFIREが考える、クラウドファンディングにおける決済体験の重要性 -執行役員CPO大橋 桃太郎氏インタビュー
個人財務管理(PFM:Personal Financial Management)
PFMは「Personal Financial Management」の略です。主に個人のお金を管理してくれるアプリやサービスを指します。銀行口座やクレジットカード、証券口座、電子マネーなどと連携して、資金の流れを家計簿ソフトに記録します。
また、2018年に改正銀行法が施行されたことにより、金融機関が保有する取引データを外部の事業者に安全に公開できるようになりました。銀行のデータを公開できるAPIを使うことで、FinTech企業により複数の口座の預け入れ・引き出しなどの情報の一元管理などが可能となりました。結果として、財務管理の効率化に繋がっています。
さらに、PFMと組み合わせることで、個人の財務状況を考慮した自動化された資産運用が実現し、初心者でも簡単に投資を始めることができます。たとえば、AIを搭載したロボアドバイザーが、最適な投資配分を提案してくれるサービスもあります。また、個人が興味のあるテーマに基づいて投資を行うことも可能です。個人の資産運用においても、FinTechによるさまざまなサービスが登場しているのです。
ソーシャルレンディング
ソーシャルレンディングは、銀行や金融仲介機関を介さず、オンラインでお金を貸したい投資家とお金を借りたい企業等をマッチングさせる仕組みです。融資型クラウドファンディングとも呼ばれ、ソーシャルレンディングの仲介者は、投資家の募集や借り手の信用審査、貸し付けから返済金の分配などを行います。
送金
〇〇Payなどの決済サービスには、個人間の送金も可能なものがあります。同じ決済サービスを使う人同士であれば、手数料なしで送金ができることが多いです。また、10万円以下の小口の送金であれば銀行間であっても送金手数料が安価になるサービスも始まっています。
参考記事:https://www.gmo-pg.com/news/press/gmo-paymentgateway/2022/0927.html
保険
インシュアテック(InsurTech)は保険(Insurance)とテクノロジー(Technology)を合わせた造語で、保険分野のFinTechと呼ばれます。
人工知能(AI)を利用して業務の効率化や、健康増進型の保険など新しいサービスを展開しています。
融資・ローン
FinTechは、個人向けローンの分野でも用いられるようになっています。以前は銀行などの金融機関に実際に足を運ぶ必要がありましたが、オンラインで対応できる部分が増えたことで、住宅ローンの比較・検討、審査、限度額の決定など、本来は複雑で時間のかかる手続きが短縮され、サービスを迅速に受けられるようになっていきています。
AIを利用することで人間が対応するよりも多くのデータを参照し、より早く正確な判断ができるため、実際の審査業務にAIを取り入れる金融機関も出てきています。
会計・経理
従来の会計・経理などの財務処理では、書類の処理やシステム間でのデータ転記などの手作業が必要でしたが、FinTechを活用してこれらの業務の効率化・迅速化を行うことが可能になりました。これらの業務は煩雑で時間がかかり、人的ミスが発生しやすいという課題がありましたが、クラウドベースの会計ソフトを利用することで、人的な作業の割合を大きく減らすことができます。業務の効率化が図れるだけでなく、紙ベースで行われていたやりとりがデジタル化されることで、社内や取引先、銀行、監査法人などの、会計・経理の関係者への情報共有も容易になります。
セキュリティ
FinTechにおいて、セキュリティは欠かすことのできない要素です。高度化している金融犯罪に対抗するため、AIによる不正アクセスの検知やフィッシング攻撃対策、不正ログイン防止サービス、生体認証システムなどが提供されています。これにより、企業や銀行、エンドユーザーのなどの利用者は安心して金融サービスを利用できるようになっています。
金融データ
金融市場や経済情勢の判断に必要な情報は、株価や為替レートなどの市場価格、物価指数などの経済統計、企業の決算開示や、日々のトレンドに関わるニュースなど、情報源や形態が多岐に渡り、なおかつ量も膨大です。そういった金融データを一括でわかりやすく提供するプラットフォームや、情報を分析するサービスにおいても、FinTechが広く活用されています。
最近では、投資家が投資判断のために利用してきたデータだけでなく、ニュースやSNSの投稿、クレジットカードの利用情報や位置情報などの消費者データなどの「オルタナティブ・データ」と呼ばれる新しい種類のデータの取り込みが進んでおり、このデータの収集や分析にもFinTechが重要な役割を果たしています。
FinTechのメリットとデメリット
FinTechの導入には、金融サービスのコスト削減や業務効率化といった多くのメリットがあります。たとえば、ネット決済を活用することで、時間や場所に縛られることなく買い物ができ、電子マネーを使用することで送金手数料が無料になるケースもあります。また、電子マネーの普及は現金取扱いの減少をもたらし、これにより現金輸送コストの削減や犯罪抑止といった防犯面での効果も期待されています。
さらに、金融インフラが十分に整備されていない新興国でも、スマートフォンを活用したFinTechサービスが急速に広がり、多くの人々に金融アクセスを提供する一助となっています。これにより、従来の銀行サービスを利用できなかった層も金融の恩恵を受けられるようになっています。
一方で、FinTechにはデメリット(課題点)も存在します。その一つが、インターネット環境に依存している点です。ネットが使えない環境ではサービスの利用が制限されるため、地域や状況によっては利便性が損なわれる場合があります。また、オンライン上でデータをやり取りする特性上、個人情報の漏洩や不正アクセスといったセキュリティリスクがつきまといます。このため、サイバー攻撃への防御やデータ保護の仕組みを強化することが急務となっています。
さらに、FinTechの急速な進化により、既存の法制度や規制が対応しきれない場面も出てきています。例えば、新しいビジネスモデルやサービスが次々と登場する中で、それらに対応した法整備が追いつかない場合、市場の混乱を招く恐れがあります。また、規制が未整備の分野では、利用者が適切な保護を受けられないリスクもあります。
FinTechを支えるテクノロジーの具体例
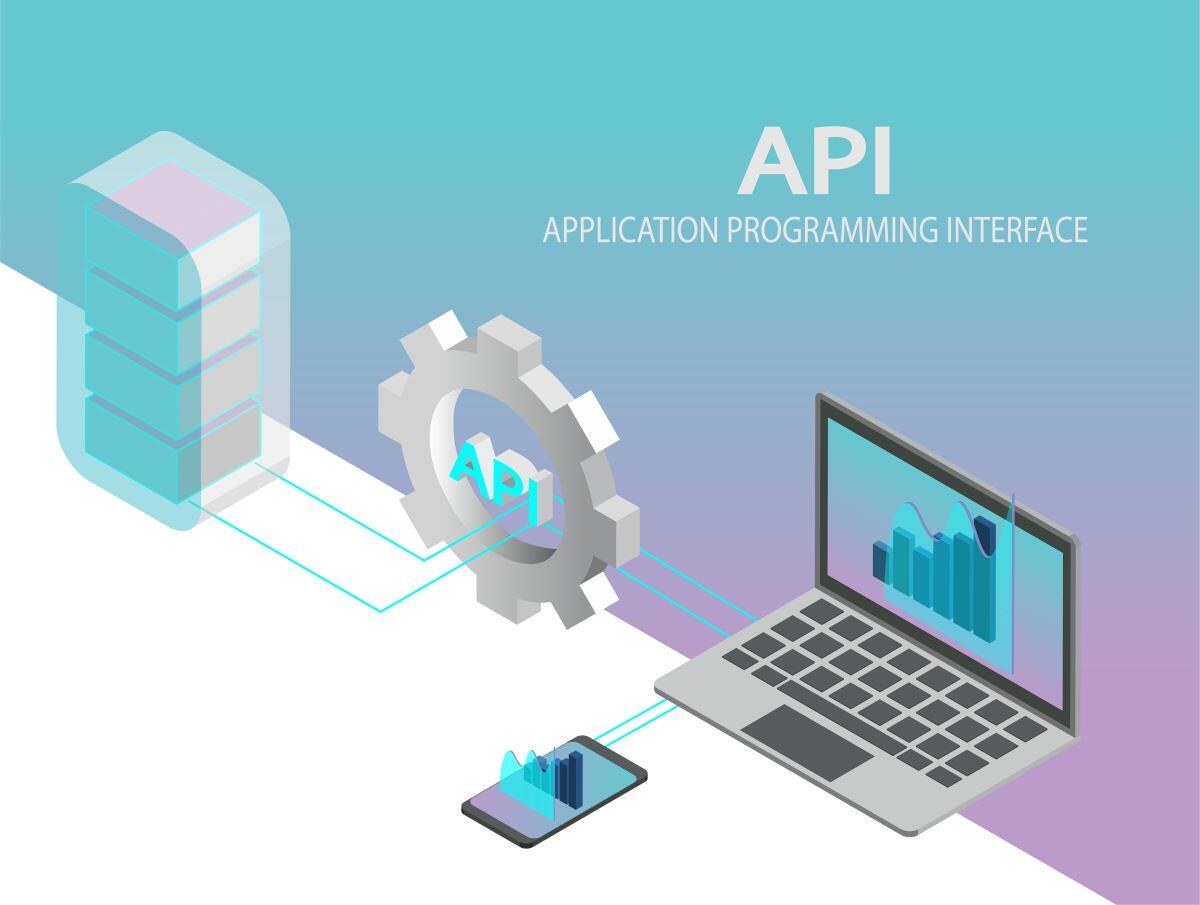
ITの技術はこれからもめざましい速さで進化し、私たちの生活に便利なFinTechサービスのさらなる拡大が期待されます。FinTechに使われている主なテクノロジーについて詳しく解説します。
ブロックチェーン
暗号資産で重要な役割を担うのがブロックチェーンです。
中央管理者を通さずにネットワーク上の端末が対等な関係でデータを共有し、システムを維持する仕組みです。
中央のサーバーで情報を一括管理するのではなく、端末同士が直接データを送信できます。そのため、中央サーバーがダウンしたりトラブルが起きたりしても、正常に動いている端末同士には影響がなく、安定した運用が続けられます。また、最大の特徴は正確な取引情報を暗号技術により1本の鎖のようにつなげることで、データの破壊や改ざんが困難かつ分散型台帳という仕組みで管理されているため、一部のシステムが停止や故障してもシステム全体に与える影響を小さく抑えられることにあります。これにより、仕組みそのものへの信頼が生まれています。
AI(人工知能)
人間の推論や認識をコンピューターで再現する技術です。チャットボットやロボアドバイザー(投資のアドバイスや必要な情報を提案してくれるサービス)、接客を行う接客型サイネージなど、すでに様々な分野で使われています。ディープラーニングにより精度が大きく向上し実用の機会が増えてきました。AIは人間では膨大な時間のかかる大量の情報を取り入れ、そこに隠れている相関関係などの特徴を発見します。その結果人間と同じような「意味」と考えられるアウトプットを提供することが可能です。
IoT
IoTは、Internet of Thingsの略です。普段の生活で身近にあるものがインターネットに繋がる仕組みを意味します。電化製品や医療機器、自動車など様々なものがインターネットに繋がることで、リアルタイムで幅広い情報を収集でき、ビッグデータが蓄積されます。
FinTechへの活用としては、例えば自動車のリースや保険において、事故時の状況を適切に分析するための情報収集に役立てることができます。
生体認証
FinTechにおいてもセキュリティ対策は非常に重要です。
認証手続きにおけるセキュリティ対策で取り入れられている技術が生体認証です。個人の静脈や指紋、虹彩、顔、音声、DNAなど様々な身体的特徴や行動的特徴を記憶させ識別します。偽造や推測が難しいため、従来のIDやパスワードなどよりも安全性が高く、様々な分野で導入されています。
API
APIは、Application Programming Interfaceの略で、インターネットや端末のアプリと外部のアプリを繋ぐシステムをいいます。例えば家計簿アプリなどで、口座の情報を連携する際、従来は人が見るWebサイトと同じテキスト情報をスクレイピングという技術を使って取得していました。結果として取得できるデータに大きな違いがない場合でも、裏で行われる処理としてはセキュリティ面やサーバーへの負荷の面で課題がありました。そこでAPIが銀行側から提供されることで、コンピューターに最適な情報を安全にかつサーバーなどへの負荷をかけず、それまでよりも高速に取得できるようになりました。
APIはあらゆるところで利用されており、世の中のサービス品質の向上に役立っています。
まとめ
FinTechは金融サービスとITを組み合わせたもので、1860年代から続く長い歴史があります。2022年現在はFinTech3.0と呼ばれスマートフォンを中心とした技術の発展によりネットバンキングやキャッシュレス決済、送金など、便利で身近なサービスとして私たちの生活を豊かにしてくれています。今後もIT技術の進化に合わせて、多くのFinTechサービスが展開されていくでしょう。
(by あなたのとなりに、決済を編集チーム)
決済業界のリーディングカンパニーであるGMOペイメントゲートウェイでは、国内や米国、東南アジアやインドのFinTech企業のイノベーションを、投融資を中心に支援しています。
特に東南アジアやインドのFinTech企業の発展は目覚ましく特に応援に力を入れています。
現地のFinTech企業にご興味がある方は以下の記事も是非ご覧ください。
また、FinTech企業を応援するメンバーの募集も随時行っています。
※本コンテンツ内容の著作権は、GMOペイメントゲートウェイ株式会社に属します。