
「後払い決済って導入すべき?どんなメリットがあるんだろう?」
ECサイトやオンライン販売を展開する店舗経営者の間で、そんな悩みが増えています。中でも近年注目されているのが「BNPL」という新しい決済手段です。顧客の購入ハードルを下げ、売上アップにつながる可能性がある一方で、仕組みやリスクが分かりづらいという声も少なくありません。
本記事では、BNPLの基本的な仕組みから導入メリット、注意点、サービス選定のポイントまでをわかりやすく解説します。自社に合った決済手段を見極めるヒントとして、ぜひ参考にしてみてください。
BNPL(Buy Now, Pay Later)とは
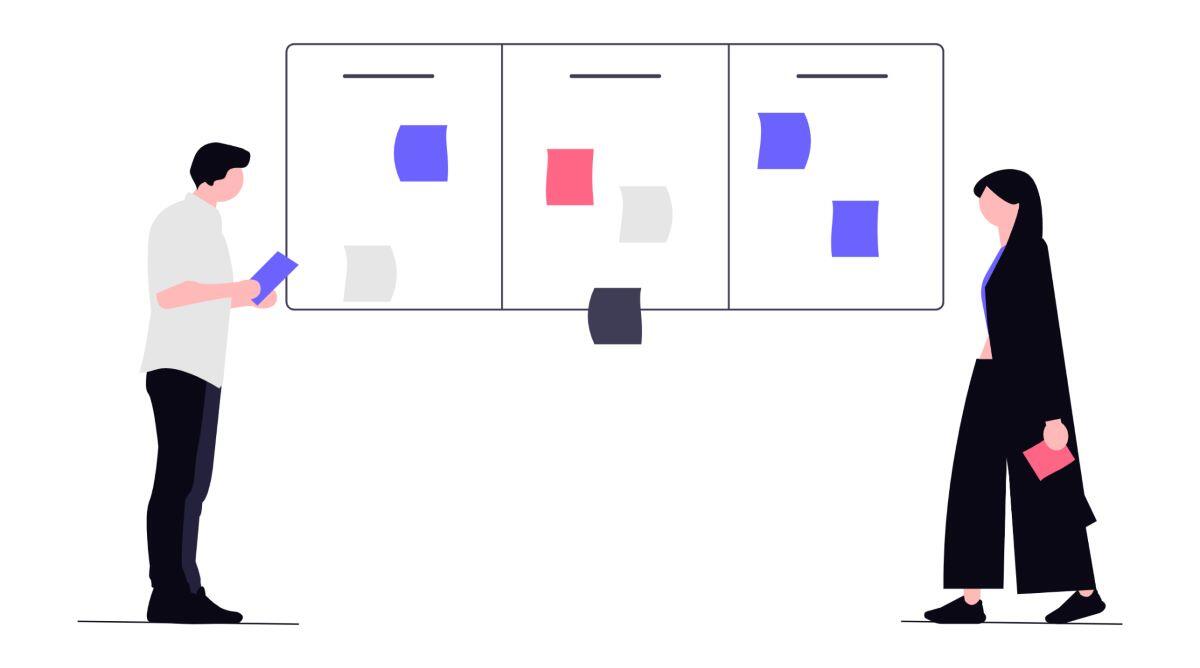
BNPL(Buy Now, Pay Later)とは?
BNPL(Buy Now, Pay Later)は、商品を先に受け取り、支払いを後日に回せる決済方式です。従来の「後払い」をオンラインやアプリで簡単に使える形にしたもので、支払い方法としてはコンビニ払いや銀行振込、分割払いなど複数のスタイルに対応しています。
事業者は、BNPLサービスを通じて代金を先に受け取り、購入者に商品やサービスを提供します。
BNPLには、分割払いや一括後払いなど、複数の支払いスタイルに対応しているものが多く、多様化している購入者の支払い方のひとつとして注目されています。
世界的に見たBNPLの状況
BNPLは2020年以降、グローバルに普及した支払方法です。
クレジットカードの普及率が高い欧米においては、カードの分割払いの手数料や利息を減らしたいという消費者ニーズがあり、特定の分割回数であれば諸費用がかからないBNPLが代替手段として支持されました(※1)。また、クレジットカードを持つことが難しい外国人労働者にとっては、主要な支払い手段になり得た点が評価されたと考えられます。
また、クレジットカードがあまり普及していない東南アジアにおいては、BNPLがクレジットカードの代替として普及したという側面もあったようです(※2)。
日本国内でBNPLが注目されている背景
日本でも、BNPLの多くが手数料無料の分割払いに対応している点はグローバルと同様ですが、普及した背景には日本ならではの事情があります。
日本ではカードの普及率は高いものの、「入力の手間」「情報流出の不安」などを理由にカードを避ける層も少なくありません。そうした人々にとって、BNPLは電話番号やメールアドレスで簡単に登録でき、SMS認証で決済を完了できる点が支持されています。
・簡単な登録・決済: アプリを通じて電話番号やメールアドレスだけで登録でき、決済時もSMS認証でログイン・支払いが完了
・利便性の高さ: クレジットカードと同様に翌月払いや分割払いが可能で、特定の支払回数の場合は手数料を無料で提供
さらに、BNPL独自のポイントサービスや、三井住友カードとGMOペイメントサービスが提供する「アトカラ」のように、Vポイントなどの既存の共通ポイントと連携するサービスも登場しています。こうしたサービスの利便性も、日本におけるBNPL普及の後押しになっていると考えられます。
さまざまな購入者のニーズに応えられるBNPLの導入を検討するために、基本的な仕組みを理解しましょう。
BNPLの仕組み
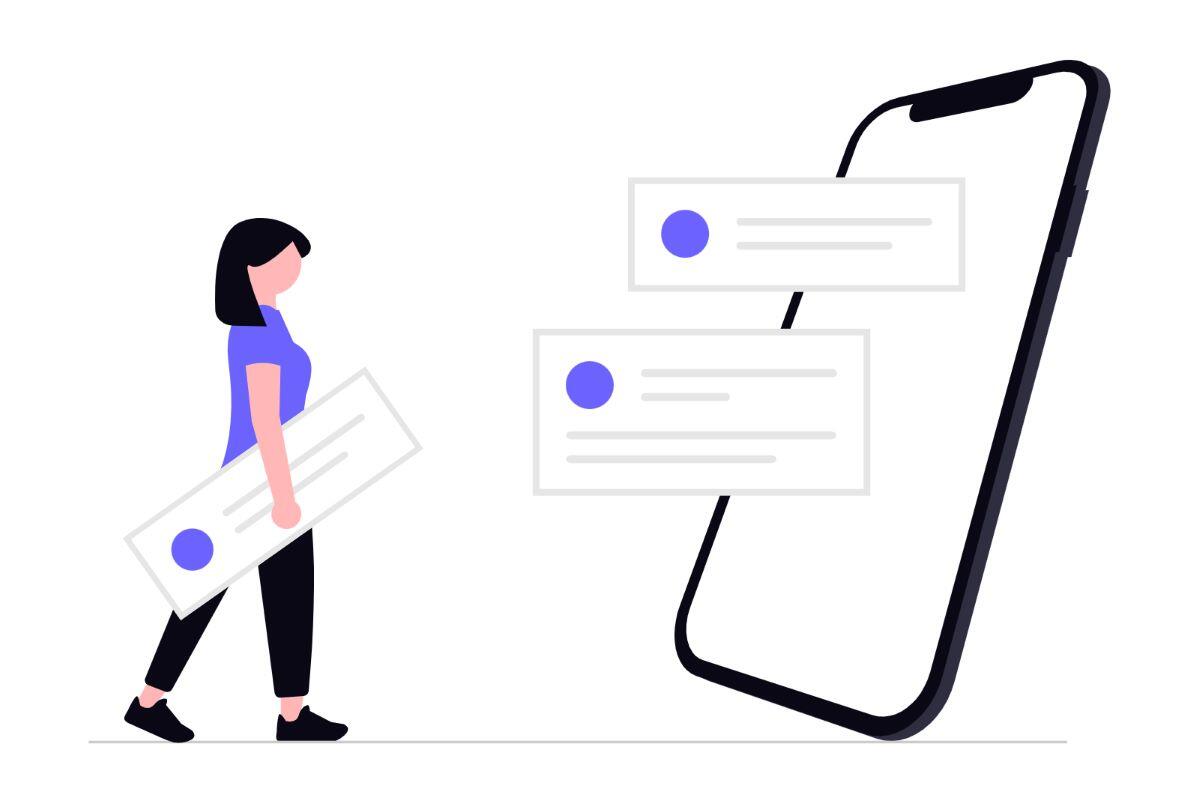
BNPLの基本的な仕組み
BNPLの基本的な仕組みは、購入者が商品を注文した時点では支払いを行わず、後日決められた期日に支払うというものです。事業者は、BNPLサービス提供会社から代金を先に受け取るため、未収によるキャッシュフローへの影響はありません。
購入者の支払いは、BNPL事業者が管理し、回収/督促を独自に行います。リスクが低く、事業者が安心して導入できる決済手段だと言えるでしょう。
BNPLの決済フロー
BNPLの流れはシンプルです。
- 利用者が商品を注文し、決済手段としてBNPLを選ぶ
- サービス提供会社が与信を確認し、承認されると注文が確定
- 事業者は代金を受け取ったうえで商品を発送
- 利用者は期日までに代金をBNPL事業者へ支払う
この一連の仕組みにより、店舗側は売掛リスクを負わずに販売できます。
BNPLとクレジットカード決済の比較
BNPLとクレジットカード決済には、いくつかの違いがあります。
クレジットカードは、利用者がカードを申し込む際に、カード会社が利用者を審査し与信枠を設定します。利用者(購入者)は、その与信枠の範囲内で利用・支払いを行う仕組みです。
一方、BNPLは、クレジットカードにおける審査よりも簡易的な審査が実施されるか、審査自体がない場合も存在します。
BNPLは利用や登録もアプリから携帯電話番号とメールアドレスなどの少ない情報で行うことができ、クレジットカードの申し込み・審査を避けたい層や、クレジットカードを持てない若年層などが取り入れやすい支払い手段と言えます。
こうした点を踏まえ、事業者はBNPLを導入することで、これまでリーチできていなかった顧客層にアプローチできる可能性があります。
BNPL導入のメリット
BNPLを導入することで、事業者は複数のメリットを得られます。主な利点としては、顧客層の拡大、客単価の向上、そしてカゴ落ち率の低減が挙げられます。
決済手段の選択肢が多い方が顧客ニーズをくみ取りやすくなり、結果として購買率が高まる傾向もあるので、BNPLの導入により、顧客満足度の向上と売上最大化を同時に目指すことができるでしょう。
顧客層の拡大
BNPLを導入することで、これまで取りこぼしていた顧客層にアプローチできるようになる可能性があります。前述の通り、クレジットカードを持たない・使いたくない利用者や、若年層、支払いタイミングに柔軟性を求める層に対して有効です。
BNPLは、簡易な審査で利用できるため、幅広い消費者が使いやすい決済手段と言えます。結果として、事業者は新規顧客の獲得につながり、販売機会を広げることが可能になるでしょう。
客単価の向上
BNPLの導入は、客単価の向上にも寄与します。
前述の通り、BNPLは分割払いに対応しているので、高単価の商品の購入を検討しやすくなります。事業者にとっては、1回の取引で得られる売上が増えるため、収益性の改善にもつながります。
カゴ落ち率の低減
BNPLは、前述の通り、クレジットカードを持たない・使いたくない層や、高単価商材の購入を見送っていた利用者に対して購入への心理的ハードルを下げる効果があります。その結果、カートに商品を入れたまま離脱する「カゴ落ち」の発生率を抑えることができます。
BNPLは、購入完了率を高めるための施策としても有効である点を踏まえて検討しましょう。
BNPL導入時の注意点
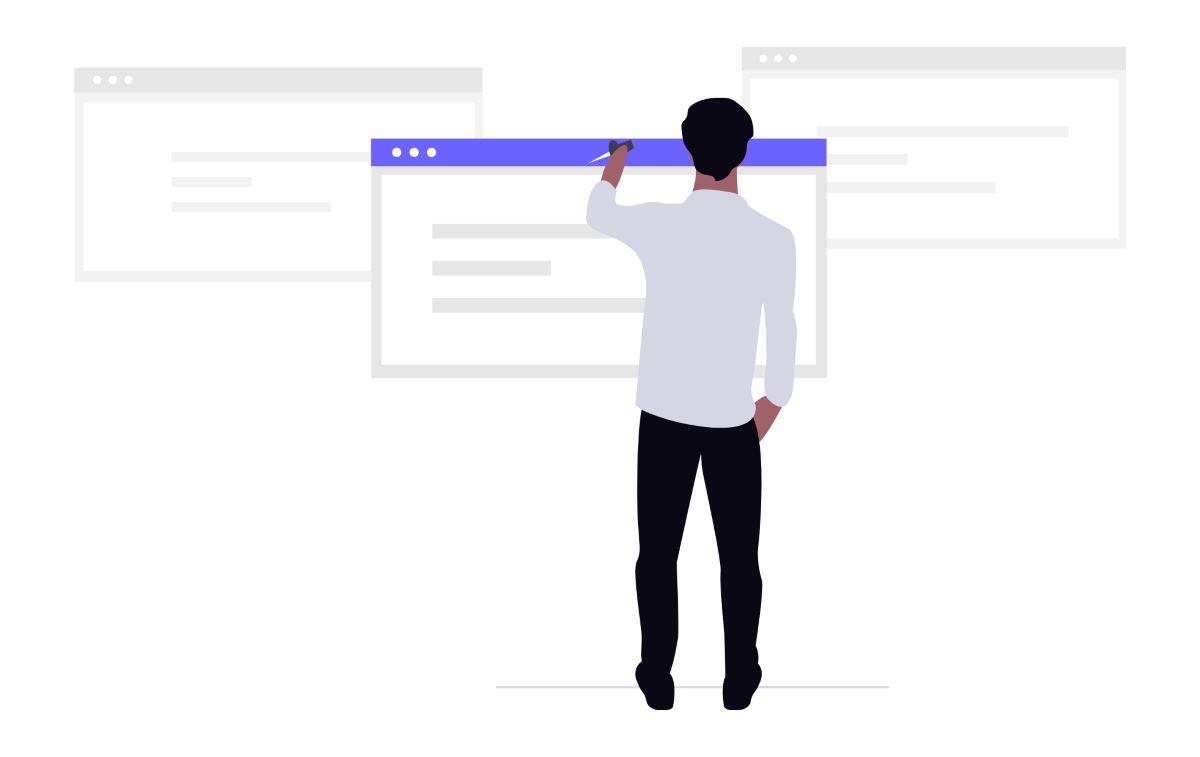
BNPLは多くのメリットがある一方で、導入にあたって注意すべき点も存在します。特に、手数料の負担、貸し倒れのリスク、そして法規制の動向については事前に確認しておく必要があります。
これらは、事業者の収益性や運用体制に影響を与える可能性があるため、慎重な検討が求められます。BNPLを効果的に活用するためには、メリットだけでなくリスクも踏まえた上で、適切なサービスを選定することが重要です。
下記でそれぞれの注意点について解説していきます。
手数料の負担
BNPLは導入ハードルが低い反面、決済手数料が利益率に影響する点は要注意です。とくに薄利多売型の商材を扱う場合は、数%の料率でも収益を圧迫する可能性があります。また、今後は多重債務対策などを目的とした規制強化の可能性があるため、制度変更への備えも必要です。多くのBNPL事業者は、決済ごとに一定の手数料率を設定しており、売上の一部が差し引かれる仕組みとなっています。
この手数料は、サービス内容や提供会社によって異なるため、比較検討が欠かせません。特に、利益率が低い商品を扱う場合は、手数料の影響が大きくなる可能性があります。
導入前には、手数料の詳細を確認し、収益への影響をシミュレーションしておきましょう。
法規制の可能性
BNPLは新しい決済手段であるため、今後の法規制の動向にも注意が必要です。現在は比較的自由な運用が可能ですが、多重債務の防止など、消費者保護の観点から、規制が強化される可能性があります。
特に、与信審査の基準や情報開示の義務などが法的に定められることで、事業者の対応が求められる場面が出てくるかもしれません。導入を検討する際には、最新の法制度や業界動向を把握し、柔軟に対応できる体制を整えておくことが大切です。
法規制の変化に備え、継続的な情報収集を行うようにしましょう。
BNPLサービスの選び方

BNPLサービスを選ぶ際は「コスト・与信枠・サポート・セキュリティ」の4点を軸に比較検討するとよいでしょう。特に与信枠は商材価格とミスマッチが起きやすいため、高単価商品の場合は上限額が十分かどうかを事前に確認しておくことが欠かせません。特に、導入コスト、対応している決済手段、顧客サポート体制、そしてセキュリティ対策の有無は、選定時の大きな判断材料になります。
これらは、事業者の運用負担や顧客満足度に直結するため、慎重な検討が求められます。下記では、BNPLサービスを選ぶ際に確認すべきポイントについて、それぞれ詳しく解説していきます。
導入コストは適正か
BNPLサービスを選ぶ際は、導入コストをしっかり比較する必要があります。初期費用や月額の固定費用などを確認しましょう。
また決済ごとの手数料率もサービスによって異なるため、売上規模や商品単価に応じた選定が求められます。事業者は、費用対効果を見極めながら、無理のない範囲で導入できるサービスを選ぶようにしましょう。
顧客サポート体制は充実しているか
BNPLサービスを選定する際は、顧客サポート体制の充実度も確認しておきましょう。BNPLは比較的ほかの決済手段よりも歴史の浅いサービスであるため、購入者側が慣れておらず、購入や支払い時にトラブルが発生する可能性も考えられます。
購入者が支払い方法や請求内容について不明点を感じた際、迅速かつ丁寧な対応が求められるため、サポート窓口の有無、対応時間、FAQの充実度などを事前にチェックしておきましょう。
与信枠(利用限度額)は商材/サービスに合致しているか
導入するBNPLにより、与信枠(購入者の利用限度額)の設定は異なります。自社の商材価格と、導入するBNPLの与信枠がマッチしていないと、そもそも利用できるシーンがないといったことになってしまいかねません。
三井住友カードとGMOペイメントサービスが提供する「アトカラ」は、会員登録のない都度与信型であれば5.5万円まで、会員登録を行うことで最大50万円/最大分割回数36回と、高単価の商材までカバーしています。
セキュリティ対策は万全か
BNPLサービスを導入する際は、セキュリティ対策が十分に施されているかを確認することが不可欠です。個人情報や決済情報を扱うため、暗号化通信や不正利用防止の仕組みが整っているかをチェックしましょう。
また、BNPLサービス提供社側から情報漏洩やサイバー攻撃への対応方針が明確に示されているかも重要なポイントです。事業者は、安心してサービスを運用するために、セキュリティ面で信頼できる事業者を選ぶようにしてください。
まとめ
BNPLは「買いたい気持ち」と「今は払えない」というギャップを埋める仕組みです。売上拡大や顧客満足度向上につながる一方で、手数料や法制度などの課題も存在します。導入を検討する際は、自社の商品特性と顧客層を踏まえ、最適なサービスを選択することが重要です。支払いを後回しにでき、なおかつ分割できる仕組みは、購入者の心理的ハードルを下げ、売上拡大や客単価の向上につながる可能性があります。
また、BNPL事業者が与信審査や請求業務を代行することで、事業者の運用負担を軽減できる点も魅力です。一方で、手数料などの注意点もあるため、導入前にはサービス内容をしっかり比較し、自社に合った選択をすることが大切です。
BNPLは、今後のECサイト運営において、顧客満足度と収益性の両立を目指すための重要な選択肢となっていくでしょう。
BNPLをはじめ、EC事業に必要となる多様な決済手段を導入できる「PGマルチペイメントサービス」は、国内トップシェアの実績を持つ決済システムです。三井住友カードとGMOペイメントサービスが提供する「アトカラ」の導入を検討の方も、お気軽にお問い合わせください。
※1...財務省『日本におけるBNPLの成長性について』
※2...国民生活センター『多様化・重層化するキャッシュレス決済 第12回 後払い決済(BNPL)』
※参考:日本貿易振興機構『米消費者金融保護局、後払い決済サービス(BNPL)事業者に対する規制発表』
※参考:野村総合研究所『BNPL(後払い決済)に潜む課題と 普及に向けた対策』
(by あなたのとなりに、決済を 編集チーム)
※本コンテンツ内容の著作権は、GMOペイメントゲートウェイ株式会社に属します。






