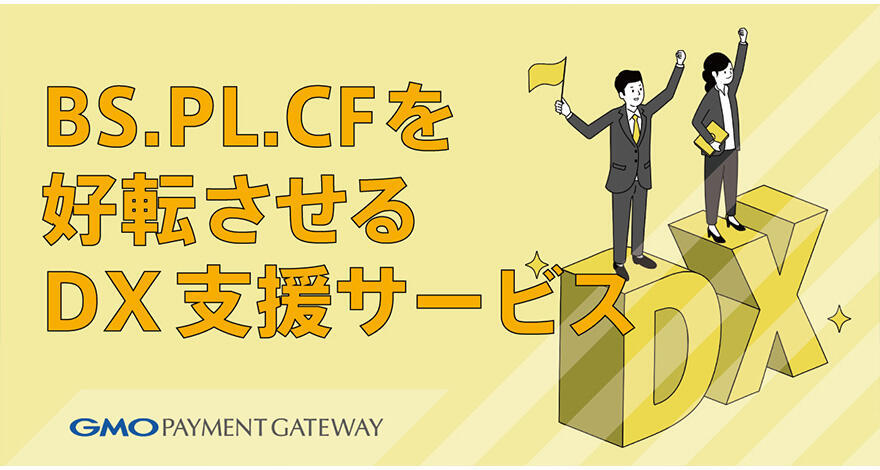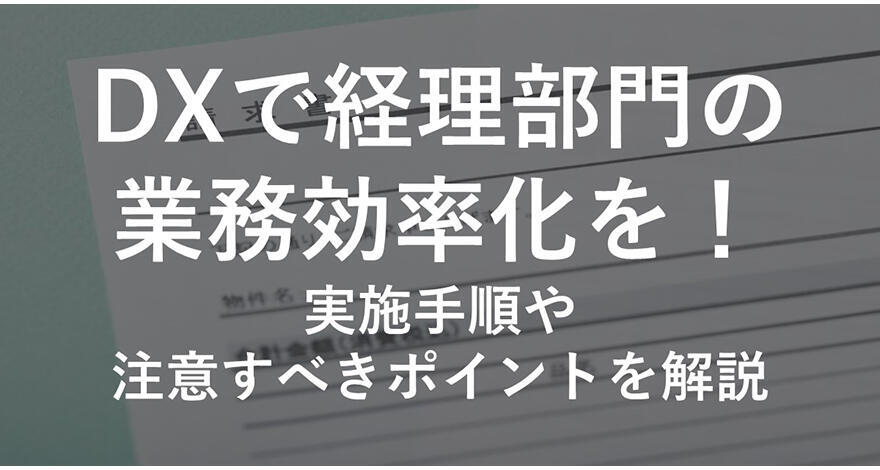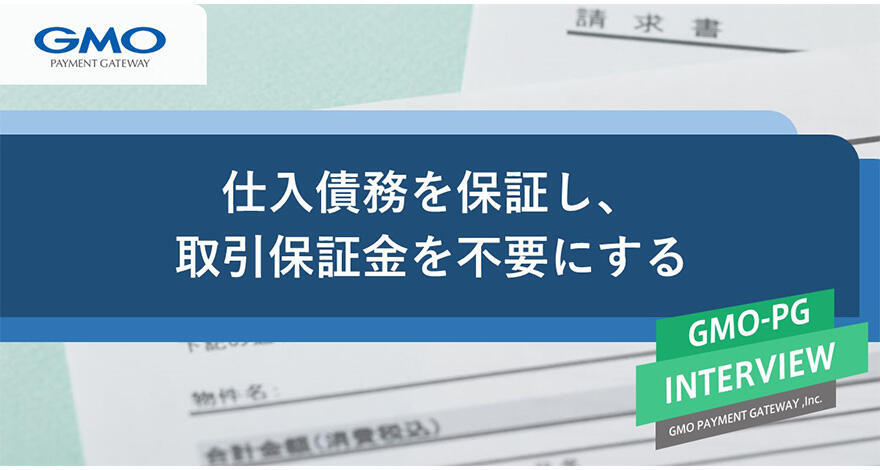DX(デジタルトランスフォーメーション)について考えてはいるけれど、何から取り組めばよいのかわからず、悩んでいる方もいるのではないでしょうか。本記事では「DXの取り組みが急務とされている理由」をはじめ、「有効な取り組み手順」や「今後の課題」「進捗状況の確認方法」などについても詳しく紹介します。
1.DXの取り組みが急務なわけ

まず、DXの取り組みを急がなければならないと考えられている理由について3つご紹介します。
1-1.「2025年の崖」リスクに対応するため
2018年、経済産業省が「DXレポート~ITシステム『2025年の崖』の克服とDXの本格的な展開~」というレポートをまとめ、発表しました。「2025年の崖」は、そのレポートの中で初めて使用された言葉で、一つの区切りを表す言葉です。ポイントとなるのは「レガシーシステム」です。「レガシーシステム」は旧来の技術によって作り上げられたシステムを指し、「技術面の老朽化」「システムの肥大化・複雑化」「ブラックボックス化」などの問題を引き起こすと懸念されています。
2025年頃には日本の企業全体のシステムのうち6割が「レガシーシステム」になると予想されており※1、「レガシーシステム」が残存している状態で「システムを理解できる人材が引退」「メーカーのサポートが終了」になった場合、データの損失やシステムダウンなどのトラブルが発生しやすくなるため、システムの刷新が必要とされています。
※1 参考:経済産業省 「DXレポート ~ITシステム「2025年の崖」克服とDXの本格的な展開~」
1-2.消費者の行動変化に対応するため
消費者の行動は常に変化しており、たとえば、車に関しても自家用車を購入するのではなくカーシェアリングを利用するなど、シェアリングエコノミーやサブスクリプションと呼ばれる継続課金モデルのサービス市場が拡大しています。つまり、「モノ」の所有よりも、体験である「コト」を重視する意識が強まっていることで、品質が良い商品を開発するだけでは売上アップにつなげることがより難しくなっているのです。
競合他社も多く、その中で勝ち抜くためには消費者目線で開発する商品・サービスが必要です。消費者のニーズを正確に知るためには、情報収集が鍵になります。ただ、莫大な情報量を収集し、分析をするのは人力では困難です。膨大なデータを蓄積するビッグデータの活用をするために、システムを抜本的に見直す必要があるのです。
1-3.頻発するデジタル・ディスラプションに対抗するため
「デジタル・ディスラプション」も注目すべきことの1つだと考えられています。デジタル・ディスラプションは「デジタルの創造的破壊」と言い換えるこができます。「新しいデジタル技術やビジネスモデルがうまれることによって、既存サービスや商品にも変化が起きる」という状況を指しています。
新規参入したITベンチャー企業が旧来の市場で優位になることも少なくありません。こういった新規参入企業は「デジタル・ディスラプター」と呼ばれています。「デジタル・ディスラプション」が起きる回数は右肩上がりとなり、既存企業はそれに対抗しなければならない状況です。新しいデジタル技術やビジネスモデルに対抗するためにもDXの推進は必須であり、急務となっています。
2.DXの取り組みを進める手順
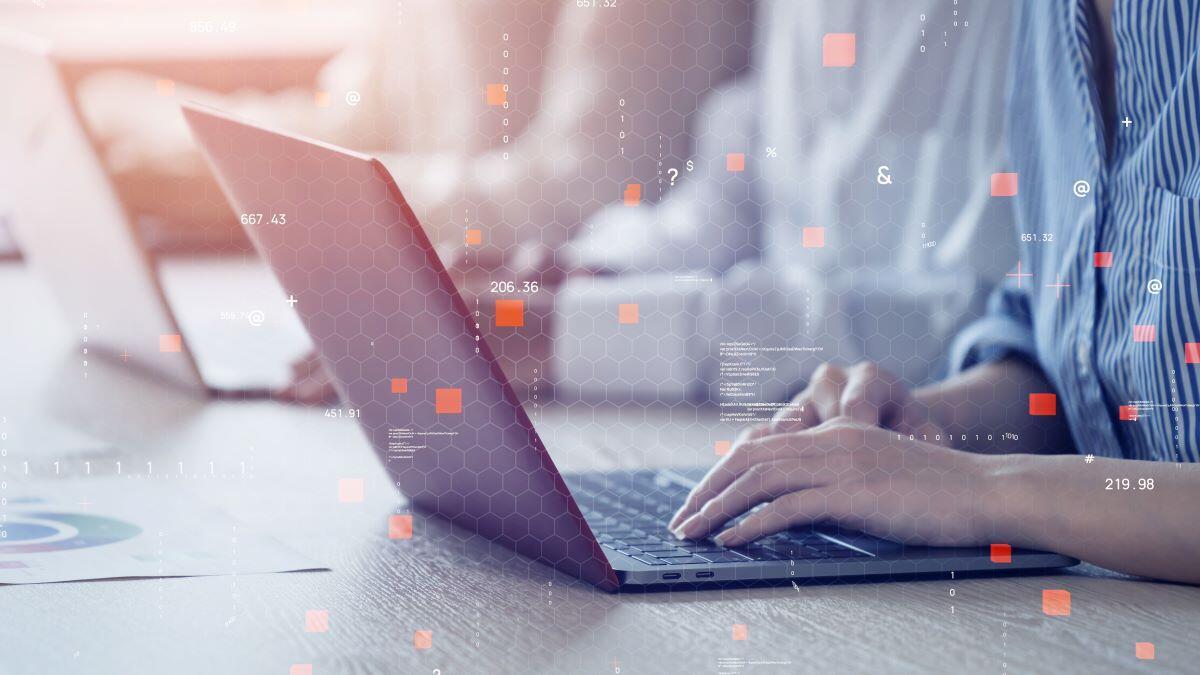
DXの取り組みを行うにあたり、どのように進めていけばよいのか手順についてご紹介します。
2-1.経営層のコミットメントを確実に得る
DXの取り組みの成功には、消費者視点のビジョンを持つことが必要です。また、会社全体で協力し合うことが重要になります。特に、経営陣がDXの重要性を理解したうえでコミットすることは、プロジェクトの円滑な進行には必要不可欠といえるでしょう。
DXの取り組みは成功するまで繰り返し行わなければならないため、資金的な投資も必要です。経営陣の支持が得られなければ、資金問題で取り組みがとん挫することにもなりかねません。さらに、経営陣には経営方針を明確にし、トップダウンでDXの必要性を社内に理解してもらう役割ももとめられます。
2-2.DXの目的を明確にする
DXの取り組みは他社より優位な立ち位置を確保し、数ある競合他社の中で消費者の心をしっかりつかむことが目的といえます。そのためには、あらたなビジネスモデルを作り出すことが必要な場合もあります。
その際重要になるのは、ビジョンや経営戦略です。何を実現するためにDXを行うのか。ビジョンや経営戦略により、企業として向かう方向を定めなければ、従業員の支持は得られず、DXを実現するための行動をできません。
2-3.DXを推進するための体制を作る
「新しいビジネスモデルの推進」「システムの刷新」いずれにしても、従来のやり方にこだわっているとDXを成功させるのが難しくなります。既存のやり方に固執せず、新しい人事制度や失敗に対する考え方を見直した教育制度なども必要です。
DXを推進するための体制づくりは「IT部門拡張型」「事業部門拡張型」「専門組織設置型」の3つがあります。
デジタルイノベーションが目的であれば、IT部門の拡張もしくは専門組織の設置が有効です。事業部門拡張型の場合は主導権を握るのが事業部門であり、IT部門はサポートをする立場になります。
過去の調査によると、DXの取り組みをする際には専門組織の設置をする企業が多いことがわかっています※2。ただし、どのタイプを選択するのかは、「業種」「自社ビジネスとITがどのように関連しているか」によって変わります。
※2 参考: IDC Japan「2018年 国内企業における『第2のIT部門』の状況」
2-4.IT資産などの現状を分析・評価する
体制づくりができたら既存のシステムを全体的にチェックし、老朽化・ブラックボックス化したシステムがないかどうかを確認しましょう。これによって、既存のIT資産を改修し、維持し続けた場合に必要になる費用の試算ができます。DX実行にあたっては全社にわたってデータを活用しなければなりません。そうするためには、データを一元管理する必要があります。あらかじめ「システムを廃棄する必要があるか」「システム連携がしやすいかどうか」などを分析し、必要であればシステム連携をスムーズにできるように作り替えなければなりません。
現状の自社におけるIT資産を分析・評価する際には、後述する経済産業省の「DX評価指標」が参考になるでしょう。
2-5.既存の業務をデジタル技術で効率化
DXの取り組みを行うにあたり、いきなり新しい商品・サービスの開発やビジネスモデルの創出をすることは簡単なことではありません。そこで、既存のビジネスモデルを基に、新しいデジタル技術を課題解決のために利用することから始めましょう。業務のペーパーレス化など、無駄やムラ、無理をなくすという意味でデジタル化の活用は非常に効果的です。最終的には、業務構造全体の見直しを行いますが、その前段階としてデジタル化による業務効率化を行うことは有効です。
こちらの記事も併せてご覧ください。
▶「DXで経理部門の業務効率化を!実施手順や注意すべきポイントを解説」
2-6.デジタル化で既存業務を拡張・高度化
既存業務の「幅をひろげる」「高度化する」に関しても、デジタル化は有効です。これは従来の組織構造のままではDXの実現が難しい部分が出てくると予想できるため、人材の配置換えなど組織を変革することで業務の拡張や高度化を実現していくためです。
デジタル化に沿ったワークフローの構築を行うことは、DXに取り組むうえで重要な部分といえます。デジタル化も1度目よりは2度目というように回数を重ねるごとに業務負担を軽減できるようになるでしょう。
3.DXの取り組みを阻む5つの壁

本章では、DXの取り組みを行ううえで「壁」となり得る5つを紹介します。
3-1.経営層がDXの重要性を理解していない
今後自社にもDXの取り組みが必要であると理解している企業の経営層は多いでしょう。しかし、老朽化した既存システムのデメリットは十分に理解をしているものの、刷新するメリットも見えにくいという現状があるため、思い切った行動に出ることができない。既存システムはまだ使用できる状態のため、わざわざコストをかけて刷新しなくても、既存システムを使い改善すればDXの取り組みを行っていると考えている。といった経営層も少なくありません。DXの取り組みの鍵は経営層が握っているため、DXについて正しく理解を促さない限り成功をするのは難しいでしょう。
3-2.新しい技術の知見を持つ人材が足りない
新しい技術を取り入れるためには「外部から招く」「社内で育てる」のいずれかを選択しなければなりませんが、優秀な人材の確保自体が難しいうえ、見つかったとしてもそもそも社内で育成するのが難しい現状があります。これは、IT技術の進歩が著しいため、社内だけでは人材の育成が追いつかないことが原因です。
また、新しいIT技術の知識や経験がある人材がいても、既存システムの使用を継続していると、既存システムを理解し扱うことができる人材がリタイアするとその引継ぎをしなければならず、新しい技術や知識を活かす場がなくなるといったことも生じます。
3-3.システムが部署別に最適化され全体でのデータ連携が難しい
日本の企業の傾向として、部署ごとにシステムの最適化を行うことがあります。また、経年によりカスタマイズを何度も行ってきていることから、システムが複雑化している企業は少なくありません。それぞれの部署のニーズに合わせたシステムになっているため、部署ごとで使い勝手は良いのですが、他部署のシステムと連携がしづらいという問題点があります。
「AI」「IoT」「RPA」「ビッグデータ」などは、いわゆる最先端のテクノロジーと呼ばれているものですが、もし、それらを導入したとしても、各部署のシステムが独立し情報が連携されていない状態である「システムのサイロ化」が発生している状況は、データを一元化する際の大きな妨げになります。
それぞれのシステムが孤立していることで、全社的なデータの連携や活用が限定されてしまうため、宝の持ち腐れ状態となってしまいます。DXに取り組む際にはサイロ化問題も先に解決すべきことといえるでしょう。
3-4.既存システムがレガシーシステムなため新しいシステムへの組み換えが困難
2018年、各企業のレガシーシステムについてのアンケートが行われました。その結果、アンケートに答えた企業のうち、約8割においてレガシーシステムが残存している状態であることがわかったのです※1。レガシーシステムが残存したまま、新たにシステムを組み替えようとすると、さまざまな問題に立ち向かわなければなりません。
たとえば、「データの連携が難しい」「整理されていないドキュメントが多数ある」「多岐にわたる影響力がネックとなり、試験を何度も重ね時間がかかる」といった問題があります。これがDXの推進を妨げることにつながってしまうのです。
3-5.システムをベンダー企業に丸投げしてきたためそもそも社内にノウハウがない
日本企業のなかには、自社にITエンジニアが存在せず、ベンダー企業にシステムの開発や運用、保守などを任せている会社もあります。依頼したベンダー企業は開発経験が豊富なこともあり頼り切ってしまいがちですが、自社内にITに詳しい人材が少ないと、デジタル化による新しいビジネスモデルや事業の創出は難しくなります。
これまではその状態でも問題が起きなかったかもしれませんが、DXに取り組むとなればそうはいきません。自社にシステムのノウハウがないことは、構造や問題点を把握できないという負のサイクルを作りだします。
4.DX推進の進捗状況を確認する方法は?
DXの推進状況を確認する方法として、経済産業省の「デジタル経営改革のための評価指標(DX推進指標)」があります。こちらの指標は各企業が自社で簡単にDXの進捗状況を確認できるようにシンプルにまとめられており、自己診断しやすいのが特徴となっています。自社で進捗状況を確認しつつ、部門別で問題点の議論ができる項目が選択されているのです。
DX推進指標は「DX推進のための経営のあり方、仕組みに関する指標」と「DXを実現する上で基盤となるITシステムの構築に関する指標」によって構成されています。それぞれ「定性指標(枠組みに関わっている)」と「定量指標(取り組み状況に関わっている)」があり、定性指標に関しては全35項目となっています。
この指標には実際に執行する関係者の取り組みがチェックできる項目だけではなく、経営監督者に関する項目も用意されています。経営監督者については、担うべき役割を全うできているかどうかをチェックすることが可能です。DXの推進における「取締役会の実効性評価項目」は、実際に取締役会の実行評価に活用できる内容となっています。なお、企業の診断結果や個人情報に関して外部に公表されることはありません。
自己診断結果はIPAの「DX推進指標自己診断結果入力サイト外部リンク」から提出できます。IPAとは中立組織で、独立行政法人情報処理推進機構のことを指します。自己診断を行った後はそれだけで満足するのではなく、結果に基づいた修正を行うことが重要です。
5.既存業務の効率化から始めてみよう
もし、DXの取り組みについてすでに経営層のコミットメントを得ており、ビジョンや体制などの準備も整っている状況であれば、デジタル技術化による既存業務の効率化をはじめてみましょう。
GMOペイメントゲートウェイでは新しい価値の創造をサポートするビジネスパートナーとして、DXを支援するサービスを多数提供しています。とくに、決済に関わるDXに強みがあります。顧客へ大量の請求書を発行する業務や企業間の請求業務などの業務効率化から初めてみてはいかがでしょうか。
※本コンテンツ内容の著作権は、GMOペイメントゲートウェイ株式会社に属します。