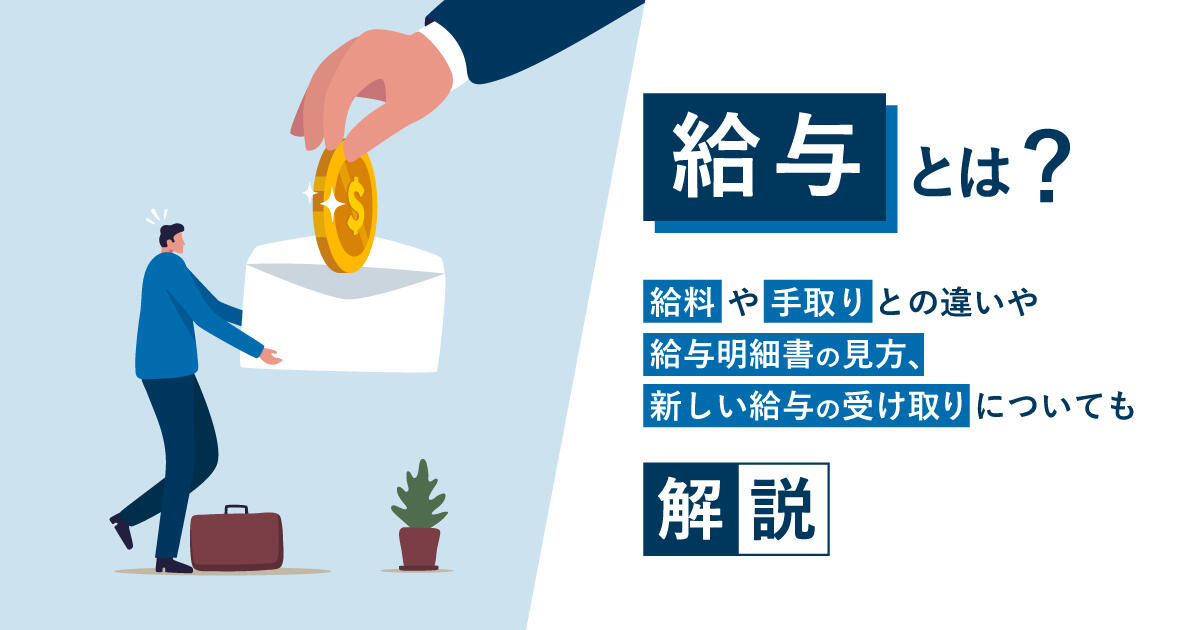
給与とは、労働者に支払われるすべての金銭を指し、基本給やボーナス、各種手当、現物支給などが含まれます。本記事では給与の概要や、手取り・給料の違い、給与明細書の見方を解説します。多様化した給与の受け取り方法についても触れていますので、ぜひ参考にしてください。
給与とは

給与とは、労働者に対して支払われるすべての金銭のことを指します。所得税法 第28条「給与所得」の規定の中で、「給与」については以下のように定められています。
給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与(以下この条において「給与等」という。)に係る所得をいう。
引用:e-GOV法令検索「所得税法 第二十八条」
上記のように、基本給だけでなく、残業代や各種手当、賞与(ボーナス)なども給与の一部とされます。さらには制服や食事、社宅などの現物給与も含まれます。このように、給与の範囲は非常に広いのが特徴です。
一方、労働基準法では、これら金銭的・物的な労働の対価をひとまとめにして「賃金」と呼びます。
この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。
引用:e-GOV法令検索「労働基準法 第十一条」
このように、制度によって「給与」と「賃金」の使い分けはありますが、日常的にはほぼ同じ意味で用いられます。
そして、労働基準法では〈通貨払い・直接払い・全額払い・毎月1回以上払い・一定期日払い〉という「賃金支払いの5原則」を定めています。
そのため、賃金は原則「通貨(現金)払い」ですが、労使協定を結び従業員本人が同意すれば銀行振込による支払いが可能です。現在は利便性や安全性の面からも銀行振込が一般的で、最近では給与のデジタル払い(資金移動業者の口座への賃金支払)や給与前払いサービスなど、受け取り方法にも多様化が進んでいます。
給料や所得、手取りとの違い
給与・賃金に関する言葉は、給料や所得、手取りなど、さまざまなものがあります。ここでは、給与とどのように異なるのか解説します。
給与と給料の違い
「給与」は基本給に加えて賞与や各種手当などを含む総称であるのに対し、「給料」は、狭い意味では毎月固定で支払われる基本給を指すケースが多い言葉です。ただし、企業によっては手当まで含めて「給料」と呼ぶ場合もあります。
労働の対価の基本となるものが「給料」で、月によって変動することはありません。ただし、企業によっては、年に一回昇給制度などで基本給が上がる場合もあるでしょう。
なお、アルバイトやパートの場合、時給や日給などが給料にあたります。
給与と所得の違い
一般的に「所得」というと、会社員の場合は給与所得を指すことが多く、給与収入(額面)から一定の控除額を差し引いた金額のことをいいます。
会社員の場合、経費の代わりに「給与所得控除」という仕組みがあります。これは会社員が給与を得るためにかかる経費を概算で認めるもので、年収に応じて控除額が定められています。計算式は以下のとおりですが、最新の給与所得控除額は、国税庁のサイトで確認しましょう。
給与所得 = 給与収入(額面) - 給与所得控除額
一方、個人事業主の場合は、業務遂行に必要なパソコンや電気代、テナント代などを経費として計上し、収入との差額を事業所得と呼びます。
参考:国税庁「No.1410 給与所得控除」
給与と手取りの違い
手取りとは、実際に受け取れる金額のことです。給与から所得税や住民税、社会保険料(健康保険、厚生年金、雇用保険など)が差し引かれた金額を指します。
基本給以外の給与の範囲とは
基本給は毎月固定で支払われる金額ですが、そのほかにも会社の制度や働き方に応じて、さまざまな手当や一時金が支給されます。ここでは、基本給以外の給与の範囲を解説します。
残業手当や通勤手当など「各種手当」
「各種手当」とは、特定の労働条件や個人の状況に応じて支払われる手当のことです。具体的には、以下のようなものが挙げられます。
| 手当 | 手当支給条件 |
| 時間外手当(残業手当) | 所定労働時間を超えて働いた場合に支給。法定労働時間を超える部分には割増賃金が適用される。 |
| 休日出勤手当 | 法定休日に出勤した場合に支給 |
| 深夜手当 | 22時~5時までに働いた場合に支給 |
| 通勤手当 | 通勤にかかる費用の補助として支給 |
| 役職手当 | 役職に応じて支給 |
| 家族手当 | 扶養家族がいる場合に支給 |
| 住宅手当 | 住宅費用の補助として支給 |
| 資格手当 | 特定の資格を保有している場合に支給 |
なお、時間外手当と休日出勤手当、深夜手当は、労働基準法第37条において該当する従業員への支払いが義務付けられています。
ユニフォームや食事などの「現物給与」
給与は原則、現金で支払われますが、一部は「現物給与」として支給されることもあります。現物給与とは、金銭ではなく、物品やサービスで給与が支払われることです。現物支給の一例を見てみましょう。
- ユニフォームや作業着
- 社宅
- 社員食堂での食事
- 自社製品
- 通勤定期券や回数券
なお、これらが給与に含まれる理由は、所得税の課税対象にあたるためです。金銭に換算した金額に所得税が課せられます。これらが現物給与に該当するかどうかは、給与明細で確認できます。
留意すべき点として、会社で支給された物であってもすべてが現物支給になるわけではありません。たとえば永年勤続者への招待旅行などは、課税されないケースもあります。
参考:国税庁「No.2591 創業記念品や永年勤続表彰記念品の支給をしたとき」
業績に合わせて支給される「ボーナス(賞与)」
ボーナスとは毎月の給与とは別に、会社の業績や個人の貢献度に応じて支給される特別な給与です。一般的に「賞与」と呼ばれており、法律での取り決めはないため企業によっては、支給されない場合もあります。
通常、夏と冬など年数回支給されることが多く、従業員のモチベーション維持につながります。基本給1.5倍や3倍など基本給に連動する賞与や、業績に合わせて変動する賞与などいくつかの種類があり、どの方法を採用しているかは企業によって異なるため注意しましょう。なお、ボーナスも、所得税や社会保険料の計算の対象になります。
手取りは給与の8割程度が一般的
会社から支給される「総支給額」(いわゆる額面)は、実際に受け取る金額とは異なります。総支給額から所得税や住民税、健康保険・厚生年金・雇用保険などの社会保険料が差し引かれたものが、いわゆる手取りです。
手取り額の計算式は、以下のように表します。
手取り = 総支給金額 -(所得税 + 住民税 + 社会保険料など)
一般的なモデルケース(独身・標準報酬月額 30 万円前後)では、税金と社会保険料は総支給額の約2~3割を占めます。そのため、実際に手元に残る手取りは総支給額の約7~8割程度が目安といわれています。扶養家族の有無や年収、保険料率によって割合は変わるため、あくまで参考値と考えておくとよいでしょう。
給与の受け取り方やタイミング

給与の受け取り方は月1回の銀行振込が一般的でしたが、近年、働き方の多様化に即して変化しています。ここでは、給与の受け取り方やタイミングについて解説します。
賃金支払いに関する5原則
給与の支払いには、労働者の権利を守るために労働基準法第24条によって「賃金支払いの5原則」が定められています。賃金支払いの5原則は、以下のとおりです。
- 通貨払いの原則: 給与は現金(通貨)で支払われること
- 直接払いの原則: 給与は労働者本人に直接支払われること
- 全額払いの原則: 税金や社会保険料などの法令で定められたもの以外は全額支払われること
- 毎月1回以上払いの原則: 給与は月に1回以上支払われること
- 一定期日払いの原則: 給与は毎月決まった日に支払われること
法律で定められた「賃金支払いの5原則」によって、労働者の権利は守られています。企業は、現金で労働者本人に直接全額を月1回以上、一定の期日までに支払わなければなりません。
給与の支払い方法は現金
賃金支払いの5原則のとおり、給与の支払い方法は原則として現金です。ただし従業員から同意を得ていれば、銀行振込での支払いが認められています。利便性や安全性から銀行振込での給与支払いが一般的です。
なお従業員の同意だけでなく、労働組合、もしくは労働者の過半数から合意を受け協定を締結しなければなりません。
給与の受け取りタイミング
給与の受け取りタイミングは「毎月1回以上、一定期日払い」という賃金支払いの原則に基づいて決められています。月1回の支払いが主流で、月末締め翌月25日払いや、15日締め翌月25日払いなどが多いでしょう。25日払いが多い理由として、口座引き落としが集中しやすかったり、給料計算がしやすかったりするためだといわれています。
なお、月2回以上の支払いが主流でない理由は、経理業務の工数が増え煩雑化しやすいことに加え、まとまった現金を準備するタイミングが増え資金繰りに負担となるためです。締め日や支払日が増えれば、労働時間の集計や残業代・各種手当の計算がその都度必要になります。また、税金や社会保険料の計算・納付は月単位や年単位で行われるため、支払い回数を増やすと処理が煩雑になるという背景もあるでしょう。
新しい働き方に合わせた給与の受け取り方
一方で近年、新しい働き方に合わせた給与の受け取り方法やタイミングが出てきています。
たとえば、スポットワークと呼ばれる働き方です。スポットワークとは、数時間などの短時間で仕事を請け負う働き方のことで、自分の空き時間に必要な時間だけ働けます。スポットワークは、仲介業者によっても異なりますがモバイル送金や銀行への即日入金、もしくはスポットワークの専用アプリ内で支払いが行われます。
そのほか、2023年4月から始まった給与のデジタル払いもあります。給与のデジタル払いとは、スマートフォン決済サービスなどを通じて、電子マネーで給与を受け取れる仕組みのことです。銀行口座をもたない人でも給与を受け取れるようになるなど、利便性の向上が期待されています。このように、働き方の多様化に伴い、支払うタイミングや回数なども変化していくでしょう。
なお、前払い、週払いなど、早く給与を受け取りたい労働者のニーズに答えている企業もあります。各種給与受け取り方法の、メリット・デメリットは下表でご確認ください。
|
給与の |
概要 | メリット | デメリット |
| デジタル払い | 電子マネーで支払われる | ・振込手数料が比較的安い ・利便性が向上する |
・希望の口座が利用できない可能性がある |
| 前払い | 給料日前に受け取れる | ・必要なときに受け取れる | ・手数料などのコストが高い ・新たに口座開設が必要な場合がある |
| 週払い | 1週間単位で振り込まれる | ・給与を早くに受け取れる | ・確定申告が必要になる場合がある |
| 即日払い | 実働日に渡される | ・すぐに給与が受け取れる | ・単発の仕事での利用中心で、利用できる場面が限られる ・確定申告が必要になる場合がある |
給与前払いサービスや、給与デジタル払いについては、以下の記事で詳しく解説しています。
関連記事:給与前払いサービスとは?導入に向けた、仕組みやメリット、選定ポイントを紹介
関連記事:給与デジタル払いとは?メリット・デメリットや導入の流れをわかりやすく解説
給与明細書で確認すべき内容

毎月届く給与明細書では、給与の内訳が把握できます。この章では、給与明細書で確認すべき内容について解説します。
勤怠状況
勤怠状況では、労働日数や労働時間、有給休暇日数などが記載されています。時間外手当などが適切に計算されているかを確認する上で重要です。残業時間などが誤っていないか、必ず確認しましょう。
支給額
会社から支払われる支給額も記載されています。基本給に加え、残業手当や通勤手当、役職手当といった各種手当の金額が記載されており、何に対していくら支給されているかが一目でわかります。
支給額は、残業や休日出勤などにより毎月変動するため、内訳を確認することが大切です。
控除額
控除額には、支給額から差し引かれる項目と金額が記載されています。主に所得税、住民税といった税金や、健康保険料、厚生年金保険料などの社会保険料が記載されています。
給与明細書だけでなく源泉徴収票も大切
給与明細書で毎月の収入を確認しますが、年に一度渡される源泉徴収票も重要です。源泉徴収票には年間所得や徴収された所得税の総額などが記載されています。
なお年末調整とは、税額の過不足を調整する手続きです。源泉徴収票には、この年末調整後の最終的な所得税額が記載されています。源泉徴収票の役割や確認しておくべき内容を理解しましょう。
源泉徴収票で所得税が確定される
源泉徴収票では、1年間の収入と所得税納付額が確認できます。所得税は源泉徴収税額表を用いて毎月徴収されていますが、あくまで正確な金額ではありません。そのため12月に年末調整を行い、所得税の支払い金額を確定します。
年末調整で所得税が確定したら、会社から源泉徴収票を受け取りましょう。なお、年末調整の結果、確定した所得税が実際に支払った金額より少なければ還付を受けられ、多い場合には追加で徴収されることもあります。
源泉徴収票で確認しておくべき内容
源泉徴収票には、さまざまな金額が記載されていますが、必ず確認すべき項目は以下の4点です。
- 支払金額: 1年間の給与総額(賞与を含む額面)
- 給与所得控除後の金額: 給与所得控除を差し引いた後の金額(課税対象のベース)
- 所得控除の合計額: 各種控除の合計額
- 源泉徴収税額: 年末調整で確定した1年間で最終的に確定した所得税額
所得控除とは社会保険料控除や基礎控除、扶養控除・生命保険料控除など、課税所得を計算する際に、課税対象から差し引くことができる控除の総称です。これにより、控除額に相当する部分は所得税の計算対象から外れます。
毎月給与から天引きされる所得税(源泉徴収税額)は、あくまで概算の金額です。源泉徴収票の「源泉徴収税額」では、1年間で受け取った給与や賞与の総額をもとに精算・確定した「年調年税額」が記載されます。
なお、源泉徴収票に記載された源泉徴収税額は、以下の計算式で算出されます。
源泉徴収税額 = ((支払金額 - 給与所得控除)- 所得控除合計) × 所得税率 - 速算控除額
実際の計算では、復興特別所得税や端数処理なども含まれるため、あくまで目安ですが、上記4点を確認すれば源泉徴収税額が妥当かを把握できます。所得税率は、国税庁の最新情報を確認しましょう。
参考:国税庁「No.2260 所得税の税率」
まとめ
給与は、会社が労働の対価として従業員に支払う「すべてのお金」を指します。具体的には、基本給だけでなく残業代や各種手当、賞与(ボーナス)なども含まれるのが特徴です。なお、実際に受け取る「手取り」は、税金や社会保険料が差し引かれています。混同しないよう、言葉の理解をしましょう。
近年働き方の多様化に伴い、即日払いや前払い、デジタル払いなどが普及しつつあります。受け取り方によってメリットやデメリットが異なるため、把握しておくとよいでしょう。
(by あなたのとなりに、決済を 編集チーム)
※本コンテンツ内容の著作権は、GMOペイメントゲートウェイ株式会社に属します。






